「できることには疑問を感じない、しかしそれは危ない」という戒めを得た
数学や英語はやればやるほど慣れてくるから、面白かった。しかしこれは法律学でいうところの刑事訴訟法や民事訴訟法の「手続き法」と同じだった。「実体法」である民法や刑法はやはりレベルが違うのだ。実体を表すものを知ってから、初めて学問が開始する。
「国語力は残酷だ」でも述べたが、英語や数学がいくらできても(中学・高校レベルでは)、それは「手順が成功」=単語の書き方・並び方、計算の正確さと筋道の立て方がうまく行っただけだ。国語力がないことがばれたら「アホ」扱いは決定なので、それだからこそ、まじめな一言一句にまでこだわる国語授業は、逆にしにくい。これは古文でも同じだ。
理屈をつけてサボっていた
高校生で古文を勉強している時「こんな、今はもう誰も話していないような『死んだ言葉』を勉強して、何の意味があるのか」と理窟をつけて、サボっていた記憶がある。
しかし中学生や高校生を指導していて、次第に「英語は確かに『今生きている言語』には違いないが、自分にとって、彼らにとって『生きている』と言えるのか? 」と思い始めた。
自分自身が英語や数学に苦手を感じなかったから、何の疑問も持たなかったくせに、苦手が出現すると、疑問を持ち始めるから、不思議なものだ。
例えば、自分たちの周りに、英語だけを使う人がうじゃうじゃいるのは、普通はあまりない。だから英語などテスト以外では意識もしない。また、DVDでアメリカ映画を見た時に、英語を聞き取っているだろうか。多くの人が「字幕」を読んだり、吹き替えにして鑑賞しているはずだ。私も面倒な時はそうしている。
「生き死に」は意味を考えるかいないかで決まる
これは、自分にとっては「死んだ言葉」と同じではないだろうか。
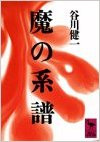
古文でも英語でも、それの意味を考えた時、「生きた言語」になるのであって、考えない時は「死んでいる言語」になる。
今存在するか・しないかの問題ではない、とようやっと気が付いたのだ。不明なこと、この上ない。
そして全く「死んでも」いないのが、古文だった。ちゃんと生きている。「我が国 日本は『死者が生者を動かす国』だ」と民俗学者 谷川健一氏は「魔の系譜」の中で喝破したが、その通りだ。とっくの昔に死んだ者たちが、動かしている。
それでも文句は言いたい
ただしやはり文句を言わせてもらうと、古典に関してはおもしろい授業をする先生に出会えなかった。完全に自分の世界に入っていて、「どこがおもしろいのか」を、全く人に教える姿勢がなかったことは証言する。今、国語教育は、実地の世界からの圧迫を受けているが、自分たちがサボっていた原因も大いにあることを認識し、反省してもらって、改良に励んでもらいたい、と思う。
私は古文については、相当に教師運が悪く、なおかつ、物がわかっていない不遜な生徒だった。これでは成績など良くなるわけがない。その上、自分で事物を考えていなかったし、古典分野の読書量も乏しかった。このブログ中で紹介した女子生徒は、自分から探したか、誰かに勧められたかは不明だが、良書と出会えたことから道が開けたのだろう。後で聞いたところによると、志望校に合格したとのこと。しかしその後は知らない。今になっては名前も忘れてしまったが、それでも私に大きな「プレゼント」をくれたわけだから、大いに感謝している。
もう少し続く。






